皆さんこんにちは
今日からいよいよ法令上の制限、建築基準法の用途規制、防火地域・準防火地域について見ていこうと思います。
勉強している方で、テキストの用途規制の部分で、こんな表を見た方はいらっしゃるかと思います。理想から言えば、この表は全部覚えていただくというのが一番いい訳なんですが、でもご存じのように、建築基準法って問題2問しか出されないですよね。で、この表を隅から隅まで覚えろっていうのは、さすがに効率が悪すぎます。この用途規制で大事なのはこの表の×を暗記するというよりはこの「境目」をクローズアップして、その境目のグループ分けがどういう風になっているのか、ということを覚えるのがポイントになります。
今日は用途規制において、この「境目」の部分を特にみっちりやりたいと思いますので、よろしくお願いします。
用途地域というのは都市計画法でも散々13種類出てきましたので、覚えておいでの方もいるという風に思いますが、その土地の使用目的に合わせた建物を建てましょう、というグループ分けでした。この用途規制は、その用途地域というグループに沿った建物を建ててください、ということになります。
まず13種類ある用途地域、この全ての用途地域に建築できるものを、見ていきたいという風に思いますが、まず宗教施設については、どこに建ててもいいということになっています。これはもう言うまでもないですが、信教の自由、これは憲法で保障されている国民の権利ですから、それをまず尊重するということになっています。続いての交番・電話ボックスと、この辺は人のいるところでないと不便というか、困りますので当たり前かと思いますが、続いての診療所、ベッド数19以下となっているところにご注意ください。実は別に病院っていうのがあって、こちらは住居専用地域と工業系用途地域に建築はできませんが、診療所は人の住むところに近いところにあった方がいい、ということで住居専用地域でも建築できますし、工場とかで社内の診療所があったりするじゃないですか。そういうわけでどこでもあった方がいいだろうということで、どこでも建築可能ということになっていますこの辺ポイントになっていますので十分ご注意ください。続いて銭湯、これは住居系用途地域では当たり前ですが、工業系用途地域でも工場の従業員が埃まみれの体をきれいにして、汗を流して帰るなんてことは十分あり得ますから、建築可能ということになっています。あと保育所ですね。これは幼稚園は含みませんのでご注意ください。保育園は例えば会社内の保育所というのもありえますから、どこでも建築できることとされています。ご存じかと思いますが最近こども園というのがありまして、これは幼稚園と保育園の統合型ということになっていますから、保育園の一部として取り扱われています。ただ幼稚園は教育施設ということで小学校の一部ということで覚えておいてください。
続いては工業専用地域以外で建築できるものということで、ご紹介したいと思いますが、基本的な中身としては工業専用地域ですから、大型の工場とか騒音とか振動とかがあります。また大型のトラックとかも頻繁に行き交うということからすれば人が住むということにはあまり適さないわけです。したがって住居やそれに近い共同住宅、寄宿舎、下宿など、あと老人ホームや福祉ホーム、それから図書館や博物館、美術館など、静かな環境を求めているものについては、工業専用地域以外で建ててください。逆に図書館とか騒がしくないので住居系用途地域の方では建てることができるということになっています。
一応一覧表の方でも念のために確認しておきたいと思います。まずはどこでも建てられるものですね、こちらですね。続いて住宅、老人ホーム、図書館、美術館は、工業専用地域以外で建てる。保育所はどこでも建てられますが幼稚園は、小学校のところに入っていますということ、この辺がポイントになるかと思います。
続いて学校、病院ということになります。診療所のほうは先ほどお話はしましたけれども、ここでいう病院はベッド数が20以上ということになりますので、よろしくお願いします。また学校、病院については環境がふさわしくないということで、工業地域や工業専用地域での建築はできない、ということになっています。
ここでポイントなのは、学校のうち幼稚園、小中学校、高校については、第一種・第二種低層住居専用地域においても建築が可能ということ。残りの大学とか各種学校、それから病院ですね。これらについては、第一種、第二種低層住居専用地域には建築できません。ということになります。
学校があまりにも遠いと、小学生の小さなお子さんが、遠くの学校まで歩いて通うっていうことになりますかということで、特別に住んでいるところの近くにあった方がいいよね、ということになります。大学生にもなればもう成人になろうとしている人ですから、どこでも通っていけると思いますし、病院については救急車とかの出入りがあまり頻繁だと、ちょっと低層住居専用地域にはふさわしくない。騒々しいっていう風になってしまいますので、ちょっとまずいということになります。そのかわり診療所が建てられます、ということですからよろしくお願いします、ということになろうかと思います。
続いて工場なんですけれども、50平米と150平米という数字が出てきて、ピンとこないっていう方もいらっしゃるかと思いますが、皆さんご自宅の床面積から想像していただければ分かるかと思いますが、50平米だとまあ、都内のファミリーマンションぐらいじゃないでしょうかね。住むならいいかもしれませんけれども、まあ商売やるとすればかなり狭いですね。ここで工場やるって言っても、それこそ家族経営の町工場の、それも小さい方ということになろうかと思います。
続いて150平米、こちらはコンビニの中でも駐車場のない街中のビルインタイプのコンビニ、小型のコンビニぐらいをイメージしていただければと思いますが、ここでいう工場は小型の、あるいはやや中型の町工場というイメージになるかと思います。そのうち本当に小型のおじちゃん、おばちゃんがやってるような町工場の50平米以下は第一種・第二種住居地域、すなわち「専用」が外れた住居地域から建築が可能。150平米のやや中型の町工場であれば、近隣商業地域から建築可能ということになります。
ここで自動車修理工場というのが出てきますが、準住居地域、これを覚えてますかね、道路の沿道としての地域の特性にふさわしい、と言っていたわけですから、当然自動車修理工場みたいな道路からアクセスしやすい沿道に作ることができますよ、というようなことにしていかないとおかしいわけです。
この準住居地域と自動車修理工場は、セットで押さえておきましょう。
一応一覧表の方でも念のため確認をしておきたいという風に思います。まず学校の関係ですが、小中高校と幼稚園は第一種・第二種低層住居専用地域から建築可能。大学と病院については、第一種・第二種中高層住居専用地域から、建築が可能ということになります。これらは工業地域と工業専用地域での建築はできません。
次に工場ですが、本当に小さい50平米以下の町工場であれば、第一種住居専用地域から建築可能。一方150平米以下のものは近隣商業地域から建築が可能です。そしていわゆる道路の沿道での利便性から倉庫、自動車修理工場、車庫、そういったものは、150米以下であれば準住居地域から建築が可能となります。
では続いて店舗ということになりまして、かなり細かい区分になっていますから、ちょっとイメージが付かないかもしれません。面積の数字ばかりを追い求めて暗記というのはなかなか難しいと思いますので、参考までにどんなものについては右端に記しておきます。
店舗のところでの注意ですが、工業専用地域では建築することはできませんのでご注意ください。特にでやすいのは、上の三つになります。まず50平米以下の兼用住宅は、第一種低層住居専用地域から建築が可能です。これは先ほど50平米の話が工場でも出てきたんですけれども、店舗というよりは小型の売店というようなイメージに近いですね。住宅の一階の一部の軒を貸しているようなイメージで、食堂や喫茶店、理容室などを行う、許可ある場合はコンビニOKとなっていますけれども、まあ相当狭いですから、売店レベルの大きさの店舗と言った方がいいでしょう。
二番目の2階以下150平米以下の店舗は、第二種低層住居専用地域から建築が可能となっていますが、こちらは駐車場のない小型のコンビニのようなイメージ。あるいは商店街の中の小型の店舗、というようなイメージになります
三番目の2階以下500平米以下ということ。こちらについては田園住居地域から建築可能となりますが、イメージは駐車場付きの郊外の大きめのコンビニとか農産物直売所のイメージになります。
四番目、五番目はほぼほぼスーパーのイメージでよろしいかと思います。ここでわざと青の枠と赤の枠で囲んであるところ、ちょっと古くて恐縮なんですけれども、もう今はなくなっちゃいましたけど、旧大店法で青枠が第二種大規模小売店舗のくくり、赤枠が第一種大規模小売店舗のくくりになります。
第一種大規模店舗、第二種大規模店舗の違いですが、大まかに分けて、3000平米未満がスーパー、3000平米以上がデパート、みたいなイメージですね。
ちょっとイメージつかない方に、ちょっとスーパーのOKさんのHPをご覧いただきたいと思います。これOKさんの宣伝でも何でもないですが、店舗面積が載っているので、せっかくなので参考にご覧いただきたいと思いますが、例えばこの街中にある青物横丁店、これマンションの一階にあるビルイン店舗ですよね。これが928平米。写真見るとまあこんな感じ。ワンフロアの一角っていう感じですね。では続いてこれ、1500平米を超えるとだいぶちょっと大型店っぽくなってきて、郊外にある川越店これ大きな駐車場があって、まあ日曜なんか混みそうなんですけどこれ2400平米。ということで、まあ写真見るとだいぶ大型な店舗だなということがわかります。もしイメージつかない方はオーケーの店舗を利用される方で、近くのお店の大きさを参考に見てみたいという方は、参考までにご覧いただければと思います。
続いて最後の二つなんですけども旧大店法の、第一大規模小売店舗ということになりますが、ここまで大きくなるとワンフロアでは収まらなくなってきて、上の階にはユニクロとかドラッグストアとか、百均っていうようなテナントが入ってくるような、ショッピングモールとかデパートという形になってきます。
ちょっと10000平米以上と以下というくくりがちょっと違いまして、10000平米以下は第二種住居地域から建築可能。10000平米を超えるとなると、近隣商業地域、商業地域、準工業地域でしか建築ができません、ということになります。ちなみに最近色々なところでニュースに出てきているというか、まあ世間を賑わせている西武の池袋店なんですけど、こちらの売り場面積どれぐらいかというと、80000平米っていうことで、これはすごいですよね。参考までにちょっと覚えておいていただければと思います。
ということで、ここでのポイントは上の三つについては結構出てきますので、5個のイチゴは500円、5個のイチゴは500円ということで、語呂合わせで覚えていただければと思います。
またよく出てくるのは10000平米以下か10000平米以上か、というふうにですね、10000平米以下であればスーパーにテナントがくっついたようなイメージ。食べ物とか薬とか日用品とかの生活必需品を買うのに商業地域まで行かなくてもいいよね、住居地域とかで買えた方がいいよね、ということで、第二種住居地域から建築ができるようになっていますが、一方で10000平米を超えるという風になると、やっぱりデパートみたいなのは集客力があって人が集まる繁華街、すなわち近隣商業地域以上で建築可能と、こういう風に覚えておいていただければいいのではないかなと思います。
ちなみにもし近隣商業地域、商業地域、準工業地域以外で、10000平米以上の店舗を仮に建てたいといったとき、これ覚えてますかね。都市計画法の開発整備促進区が出てきましたが「じゅんこと二人で住む」と言っていたわけですが、いわゆる準住居地域、工業地域、第二種住居地域、あとは用途地域が定められていない区域については、開発整備促進区を指定してあげたら10000平米を超える劇場、店舗、飲食店等を誘致できるというわけですね。
その他になりまして、用途地域の指定のない区域に関しては、10000平米以上の店舗、飲食店、展示場、遊技場、劇場、映画館、演芸場とか、まあこれ今、開発整備促進区の中でお話しした通り、地区計画の開発整備促進区を指定してあげれば、これらは駄目なんだけれども建築が可能となります。
続いて異なる用途規制の地域にまたがる場合はどうするかというと、過半の敷地の規定が適用になります。これはそんなに難しくないかなと思います、続いてたまに出てくるのが卸売市場、火葬場、汚物処理場等については、あらかじめ都市計画で位置がここですというふうに、決められているのであれば建築ができるんですけれども、決められていなければ駄目ですということになります。突然急に火葬場が建てられるという風になったら、トラブルの元になるわけです。これもたまに試験に出てくるところですので、押さえておいてください。
最後に特別用途地区内の規制緩和ということで、国交大臣の承認を得て、条例で用途制限を緩和することが可能になります。
ここで最後になりますがおさらいを兼ねまして13種類の用途地域で、何が建てられるのか建てられないのかということについて、ちょっと一覧表と突き合わせながら簡単に復習しておきたいと思います。
低層住居系用途地域となりますが、50平米以下の住宅に付属する店舗は建築が可能です。150平米以下であれば第二種低層住居専用地域、500平米以下であれば田園住居地域から建築が可能になります。
続いて中高層住居系専用地域になりますけれども、事務所と1500平米以内の店舗、これは第二種中高層住居専用地域から建築が可能になります。
続いて「専用」が外れた住居系用途地域なんですけども、専用が外れたのでまあ住居だけにこだわらないということで、いくつかの住居以外のものの建築が可能になってきます。第一種住居地域では、ホテル、旅館やスポーツ施設系、50平米以下の小型の町工場、それから3000平米以下の小型のスーパーが建築可能、すなわち静か系の建築物ですね。一方、第二種住居専用地域になると、麻雀、パチンコ、カラオケボックス、ダンスホールなど賑やか系の施設とか、10000平米以内の中規模スーパーですね。第二種住居専用地域から建築可能になります。
続いて商業系用途地域、こちらについては、基本的になんでも建てられるという風に思っていただいて構わないんですけれども、まあ例外を覚えて頂くということになりまして、料理店、こちらについては食堂のことではなくて、歓楽街にあるキャバレーとかスナックですね。あとこちらについて個室付浴場、これはソープランドなんですけれども、こんなのが街中にあってもらってはちょっと困るということで、近隣商業地域、町中の商店街では、建築ができません、商業地域だけで建築ができますということで覚えておいてください。
続いて工業系用途地域になります。準工業地域なんですが、ちょっとご覧いただくと分かるんですけれども、準工業地域と商業地域っていうのはほぼほぼ実は一緒なんですね。で唯一違うのはここで先程でた個室付浴場、ソープランドについては、これは準工業地域はダメで、商業地域だけ、即ち歓楽街の商業地域以外は建築ができません、ということになるわけです。あと10000平米を超える店舗、飲食店ですね。これは工業地域、工業専用地域では建築ができません。これは店舗を建てるのにふさわしくないっていうよりは、せっかく工場を建てるっていうような土地なのに、目的の違う大型店舗とかが突然来られても、ちょっと工場を建てるのに迷惑という方が近いという風に思います。あと繰り返しになりますが学校系そして病院なんですけれども、工業地域と工業専用地域では建築ができません。
まあ今日お出ししたこの一覧表については、私のサイトに特別に皆さんにPDFにしてダウンロードできるようにしておきますので、有効にご活用いただければと思います。
じゃあ今日は用途規制ということでだいぶ長くなりましたので、この辺にしましてちょっと皆さん復習をしておいていただければと思います。また次回よろしくお願いします!

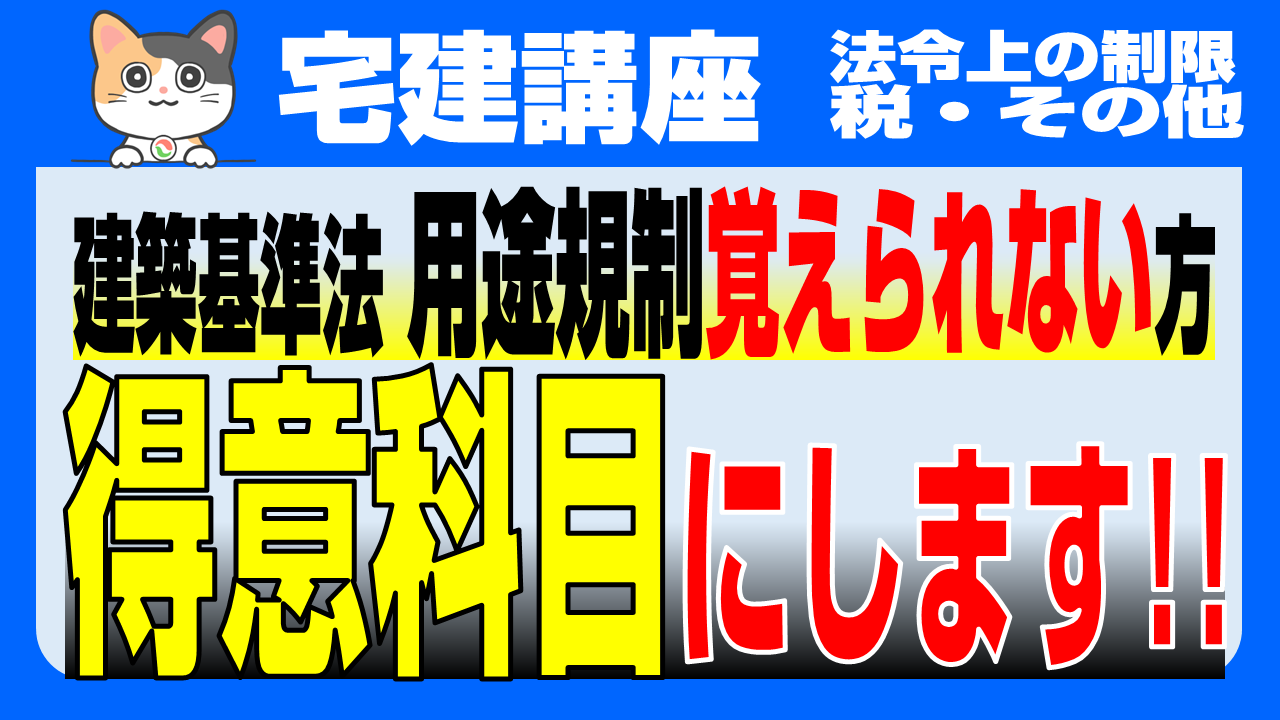
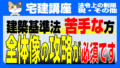
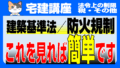
コメント